伝統的には母方の祖父母が五月人形を用意することが多いものの、現代では両家で分担や両親自身が買うなど様々なスタイルが一般的になっています♪
五月人形の準備には特別なルールがないので、両家で相談して決めるのがおすすめです!
初めての五月人形、父方と母方どちらの親が買うものなのか困っていませんか?
この記事では、どちらの親が買うべきかというギモンから、節句の意味、購入時期まで徹底解説します!
- 購入者に関する現代の考え方
- どちらの親に買ってもらうか、上手な相談方法
- 予算の相場と役割分担のアイデア
- 購入から保管まで、長く大切に使うためのポイント
- 五月人形が持つ本来の意味
初節句の準備を楽しみながら、家族の絆を深める機会にする秘訣をお伝えします♪
本格的かつスタイリッシュなデザインの五月人形♪
硬いイメージの兜をやさしいイメージに見せるラウンド型のケース!
インテリアにも馴染みやすい木目調フレームでおしゃれでコンパクト♪
五月人形はどちらの親が買う?ママとパパの疑問を解決

五月人形はどちらの親が買っても大丈夫です!
大切なのは両家の気持ちを尊重しながら、家族みんなで決めていくこと♪
特別なルールにとらわれず、ご家庭のスタイルに合った方法で決めることで、みんなが笑顔になれる素敵な初節句の思い出ができますよ♪
伝統と現代
五月人形の準備に関する考え方は、時代と共に変化しています。
昔は、男の子の初節句は母方の祖父母が担当するという考え方が一般的でした。
現代では家族の形も多様化し、両家で分担したり、パパとママが中心となって決めるなど、柔軟なスタイルが増えていますよ。
大切なのはどちらの親が買うことが正しいのかではなく、家族みんなの気持ちが尊重される形を見つけることですね♪
昔ながら
五月人形は母方の祖父母が担当するという考え方が、昔は主流でした。
昔の日本では、女性は結婚すると夫の家族と暮らすことが多く、自分の実家とは少し距離ができてしまいがちでした。
初節句は、母方のおじいちゃんおばあちゃんが可愛い孫に会える特別な日として、大切な習慣になっていました。
地域による違いもあり、西日本では母方の親が用意する事が多く、東日本では父方の親が用意することが多い傾向にあります。

時代は変わっても大切な行事、両家の想いを尊重した準備ができるといいですね♪
現代
今では様々な家族のカタチに合わせて、柔軟な対応が増えています。
現代では、両家のおじいちゃんおばあちゃんが一緒になって五月人形を選んだり、若いパパとママが自分たちの好みで選ぶケースも増えています。
また、「五月人形は母方、鯉のぼりは父方」というように役割を決めたり、それぞれの家庭に合わせて費用を分担するなど、家族のカタチに合った準備の仕方が主流に♪

夫婦で主導しながら両家の意見も聞くバランス型も人気!
ポイント
五月人形の購入者を決める際に、家族間のトラブルを避けるコツを紹介します。
早めの話し合いを心がける
初節句の準備は早めに始めるのがベスト!
遅くとも節句の3~4ヶ月前には話し合いをスタートさせましょう♪
- 突然の申し出には即答せず「家族で相談します」と伝えるのが良いでしょう
- 両家の祖父母に同時期に相談を始める
- LINEグループなどで情報共有する体制を作る

突然の申し出にはすぐ返事せず「ありがとうございます、少し相談させてください」がベストアンサー!
両家の気持ち
祖父母にとって、孫の初節句は特別なイベントですよね!
どちらの親(祖父母)も何かしら関わりたいという気持ちがあるものです。
- 五月人形以外の節句アイテム(鯉のぼりなど)の分担も検討
- 飾り付けや節句のお祝い会など、モノ以外の役割も大切に
- 購入前に実物を見に行く際は両家の祖父母も誘う
- 遠方の祖父母もビデオ通話で選び方に参加できる工夫を
役割分担することで、みんなが満足できる形できるといいですよね♪
予算
五月人形にはいくつかのタイプがあり、価格帯も様々です。
- 価格帯:3万円~10万円
- 特徴:場所を取らず、シンプル
- おすすめ:マンション住まい、収納スペースが限られている家庭
- 価格帯:10万円~30万円
- 特徴:本格的な鎧を小型にしたもの
- おすすめ:伝統を大切にしたいが、スペースも考慮したい家庭
- 価格帯:20万円~50万円以上
- 特徴:人形や小道具も含む豪華な飾り
- おすすめ:十分なスペースがあり、本格的な節句飾りを希望する家庭
分担
費用だけでなく、準備のプロセスも含めた分担方法を紹介します。
費用面での分担例
- 両家折半:最もシンプルで公平な方法
- 比率分担:「父方6:母方4」などの比率で分担
- 項目別分担:五月人形は一方が買う、鯉のぼりや飾り台はもう一方が買う

柔軟な費用分担がおすすめ!
両家の状況に応じて比率を決めると、無理なく準備できますよ♪
準備プロセスでの分担
- 情報収集:一方の祖父母が展示会情報を集める
- 選定作業:両家合同で展示会に行き一緒に選ぶ
- 飾り付け:五月人形の設置と会食準備を分けて担当してもらう
選ぶ過程も大切な思い出になりますよね♪
両家で意見を出し合いながら、準備を進めると良いですね。
室内用こいのぼり
「iroiro」のちりめん素材室内鯉のぼりが大人気 ♪
マンションやアパートでも飾りやすい小さめサイズながら、華やかな存在感でおしゃれに初節句を彩ります♪
選べる10種類のデザインで、インテリアにも馴染むおしゃれな室内用こいのぼりです!
五月人形はどちらの親がいつ購入?飾るタイミングは?

五月人形は1月中旬~2月が最適な購入時期です♪
1月中旬~2月であれば、展示会も本格化し品揃えも最大となるため、じっくり比較検討できます。
購入後の保管方法も購入時に確認しておくと安心です♪
大切な初節句の記念品なので、五月人形選びから保管まで丁寧に準備したいですね♪
時期
初節句を迎える家庭では「いつから準備すればいいの?」と悩んでしまいますよね?
五月人形は人気商品の品切れを避け、どちらの親が買うことになっても早めの行動がポイントです♪
月別の準備スケジュール
- メリット:選択肢が豊富、早期割引あり
- デメリット:展示会がまだ少ない時期
- メリット:展示会が本格化、品揃え最大
- デメリット:人気商品は早めに完売の可能性
- メリット:値引き率が上がる可能性
- デメリット:品切れ多数、選択肢が限られる
「3月再訪時には欲しかった商品が完売していた」という声もあるので、1月中に動くのがベストですよ!
どちらの親が買うと決まっていなくても、人気商品は早めにチェックしましょう♪
購入方法
五月人形は実物を見て選ぶのが基本ですが、状況に応じてネットショッピングもよいですね♪
実店舗での選び方
五月人形を実店舗で選ぶ際のメリットや特徴を紹介します。
購入場所によって異なる特色を比較してみましょう。
- 百貨店の展示会:多くのブランドを一度に比較できる上、特別価格や購入特典がある場合も♪
- 専門店:詳しいアドバイスが受けられ、専門知識を持つスタッフが対応してくれます。
- 地元の人形店:アフターケアも安心で、毎年の飾り方指導や収納方法のアドバイスも相談できますよ。

百貨店の展示会で複数のブランドを比較した後、気に入ったメーカーで詳しく相談するのが効率的ですよ!
オンライン選びのコツ
インターネットで五月人形を選ぶときは、以下のポイントを押さえると失敗が少なくなります。
- 口コミや評価を丁寧に確認: 「思ったよりも小さかった」「色が違った」などの具体的なコメントに注目を!
- 実物の写真をどちらの親にもたくさん見てもらう: 複数の角度から撮影された写真で質感をチェック!
- 返品・保証条件を必ず確認: 万が一の場合に備えて、返品可能期間や保証内容は購入前に確認しておきましょう。
- 両家で候補をシェアして意見交換: お気に入りの候補を共有すると、話し合いがスムーズに。

遠方の家族とはZOOMで候補を見せ合いながら相談すると、オンラインでも十分に意見交換ができますね♪
飾り方と時期
せっかくの五月人形、どう飾って、いつまで飾るべき?
初節句を彩る飾り方のポイントと、伝統的な飾り期間を知って、家族の大切な記念日をより素敵に演出しましょう!
飾り方のポイント
飾り方にはちょっとした工夫で見栄えが良くなるコツがあります!
五月人形は明るい場所、できれば南向きの場所に、床から1m前後の見やすい高さに飾るのが理想的です。
人形の顔は扉や窓に向けず配置すると良いとされており、五月人形が家から出て行かないようにという願いが込められています♪
南向きの明るい場所では五月人形の色合いが鮮やかに映え、丁度良い高さに置くことで家族がいつでも眺めて楽しめる、素敵な節句飾りになりますよ♪
飾る期間の目安
五月人形を飾る時期には、伝統的な考え方と現代の生活スタイルに合わせた傾向があります。
家族のライフスタイルに合わせて、無理なく楽しめる期間を選びましょう。
五月人形は伝統的には3月中旬から5月末まで飾られていましたが、現代では4月上旬から5月中旬頃に飾る家庭が多いようです。
片付ける際は、5月5日当日の片付けは縁起が良くないとされる習わしがあります。
5月5日の片付けは避けたいポイント!
「せっかくのお祝いを早々に片付ける」と縁起が悪いとされています。

「魔が去る(まがさる)」の語呂合わせから5月6日がおすすめとも言われていますよ♪
保管方法
五月人形は正しく保管すれば、長く美しさを保てます♪
でも、大切な五月人形を何十年も美しく保つためには、保管方法にもひと工夫が必要になるので、購入時に専門店からアドバイスをもらうこともおすすめですよ。
- 湿気対策:防湿剤と乾燥剤を併用
- 虫対策:防虫剤を適量使用
- 温度管理:直射日光を避け、温度変化の少ない場所に保管
- 定期点検:年に1~2回は箱を開けて状態確認
子どもの成長と共に毎年飾る大切な宝物、少しの手間をかけて長く楽しめる状態を維持してあげましょう。
将来、子ども自身の子どもへ受け継ぐことができる家族の宝物になりますね♪
五月人形はどちらの親が買う意味とは?歴史や由来は?

伝統的には母方が贈る習慣でしたが、現代では両家協力のケースも増え、子どもへの願いの形は多様化しています。
五月人形には子どもの健やかな成長と幸せを願う深い意味があるんです♪
どちらの親が準備するかという習慣には、家系の継承や家族の絆を重視する日本の伝統的な価値観が反映されています。
時代を越えて親から子へ受け継がれてきた願いが、美しい形になった伝統行事ですね!
歴史
五月人形の歴史は千年以上前から始まり、時代とともに形を変えながら続いてきました。
五月人形の歴史は平安時代に中国から伝わった端午の節句から始まり、鎌倉~室町時代には武家社会で武具や兜を飾る習慣が発展しました。
江戸時代になると庶民にも広がり、現在の形に近い五月人形が登場します。
明治以降は男児の成長を願う行事として全国に定着し、今日まで大切に受け継がれてきました。
菖蒲(しょうぶ)を飾るのは「勝負に強くなるように」という願いが込められているんです!
昔の武士たちが大切にした風習が、今の五月人形につながっているんですよ♪
五月人形の象徴的意味
五月人形の道具にはどのような意味があるのでしょうか?
- 兜:知恵と勇気、そして頭脳明晰であるように
- 鎧:外敵から身を守る強さと忍耐力
- 武具:困難に立ち向かう勇気と精神力
- 鯉のぼり:出世と成功の象徴
どちらの親が用意するにせよ、五月人形には子どもの幸せを願う気持ちがたくさん詰まっています。

時代が変わっても「強く、賢く、健やかに育ってほしい」という意味は同じですね!
家族の願い
五月人形は単なる飾り物ではなく、祖父母と孫をつなぐ温かい伝統文化です。
毎年飾る時間は、子どもの成長を祝いながら家族の絆を深める特別なひととき♪
小さな手で兜に触れる姿や、キラキラした目で人形を見つめる表情は、家族みんなの心に残る宝物のような思い出になりますよ♪
毎年、五月人形を飾る時間は、どちらの親にとっても特別な思い出になります。
子どもの成長と共に深まる家族の絆を感じる素敵な機会ですね♪
五月人形はどちらの親が買うの?まとめ

- 伝統的には母方が用意するとされていましたが、地域の風習によってどちらの親が用意するのかは異なる
- 現代はどちらの親が買うという決まりはなく状況に合わせて柔軟に決定する
- 両家の祖父母の気持ちを尊重し、早めに話し合いを始めることが大切
- 五月人形の購入時期は1月~2月がベストシーズン
- 価格帯は3万円~50万円以上と幅広いため、住環境や予算に合わせて選ぶ
- 飾る時期は4月上旬からが目安で、5月6日以降に片付ける。
- 保管の際は、湿気や直射日光を避け、適切な環境を整えることが重要
- 五月人形を「どちらの親が買うか」より大切なのは家族みんなの願いを込めた贈り物という意識が大切
初節句は子どもにとっても家族にとっても特別な記念日。
思い出に残る節句の準備は、家族の絆を深める大切な時間にも♪
両家の気持ちを大切にしながら、子どもの健やかな成長を願い、素敵な五月人形を選びましょう!
弓太刀にまでこだわった伝統的な五月人形♪
兜だけでなく弓太刀も細部までこだわった限定の組み合わせ!
コンパクトながらも気品を感じられる本物志向のセットです♪
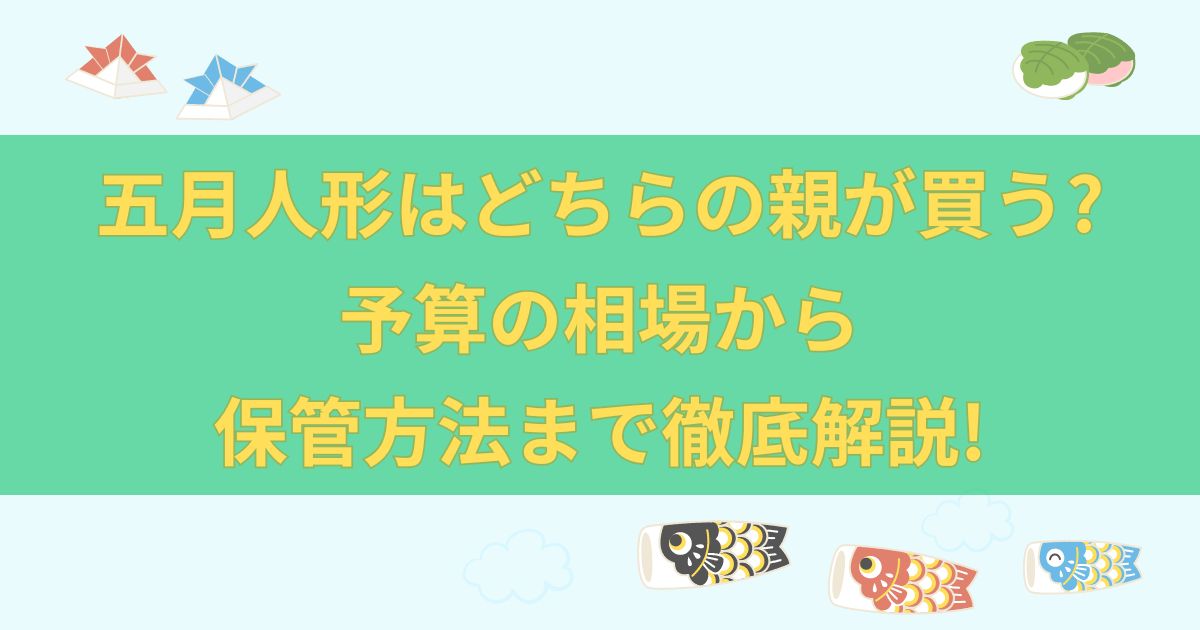



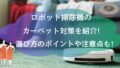
コメント