お七夜は赤ちゃんが生まれて最初のお祝いですが、家庭によって「する・しない」の選択は自由なので、ご家族で相談して決めましょう♪
出産後、育児がスタートすると、あっという間に時間が過ぎていきますよね。
お七夜はよく聞くけど、一体何をすればいいの?
準備が大変だから、しなくてもいいのか分からない、というママパパも多いのではないでしょうか。
そこで、お七夜をする、しないのメリット・デメリットを紹介します!
他にもいつするのか、流れや注意点、マナーも解説!
- お七夜とは?
- メリット・デメリット
- 流れや注意点
- 知っておきたいマナー
- その後の行事
ライフスタイルに合った方法で、する場合もしない場合も、赤ちゃんのお祝いを楽しんでくださいね!
赤ちゃんと家族の幸せを願いながら、ひとつひとつ手書きで書いてくれますよ♪
和柄と洋風があるので、好きなデザインで選べるのも嬉しいですね!
お誕生日から1年間のカレンダーもついているので、イベントがしっかり把握できる!
お七夜はする?しない?メリットとデメリットも紹介!

お七夜は生まれて最初のお祝いですが、ご家庭のライフスタイルによって、する・しないの選択は自由ですよ♪
赤ちゃんが生まれて7日、バタバタしているとあっという間。
お祝いをしたいけど、具体的に何をすればいいのかや準備などが分からないと悩んでしまいますよね。
お七夜とはそもそもどんなお祝いの行事なのか、メリットやデメリットを詳しく紹介!
家族みんなの思い出に残るお祝いにするためにぜひ参考にしてみてください♪
お七夜とは?
お七夜は、赤ちゃんの誕生を感謝し、これから健康でいられるように願いを込めてお祝いする行事。
お七夜の起源とされているのが、平安時代の「産立ち祝い」。
昔は出生後、すぐに亡くなる赤ちゃんも多かったため、無事に1週間生きられるのはとてもめでたいとされていました。
そのため無事に7日目を迎えたら、名前を付けるのがひとつの節目として、お七夜を行っていたと言われています。
お七夜をするメリット・デメリット
お七夜をするメリット・デメリットは以下になります。
- 赤ちゃんの名前を正式に発表できる
- 家族で楽しい時間を過ごせる
- 記念写真撮影ができる
- 祖父母とゆっくり会話を楽しむ機会になる
お七夜のメインイベントは命名式なので、家族で命名式を行うだけででも、素敵な時間になりますね♪
- 準備に時間がかかる
- ママの体調が不安定な時期に準備をする必要がある
- 祖父母を招く場合は交通や宿泊の手配が必要
- 豪華な料理には準備が必要
お七夜は必ずしもしきたり通りにする必要はないため、ママパパが楽な方法を考えてみましょう!
お七夜をしないメリット・デメリット
お七夜をしない場合のメリット・デメリットは以下になります。
- 準備しなくていいので、ゆっくりと時間を過ごせる
- 家族の納得のいく方法で、お祝いを楽しみながら記念を残せる
産後は何かとバタバタしがちなため、体調が戻っていないママがゆっくりと過ごせるのは良いですね♪
- 名前を正式に伝える場がない
- 記念撮影できる機会がない
- 祖父母など集まる機会がない
大きなデメリットはないですが、お七夜をしないのであれば、ご両親にはお話ししておくのがおすすめ!
お七夜をするのはいつ?基本的なやり方や流れを解説!
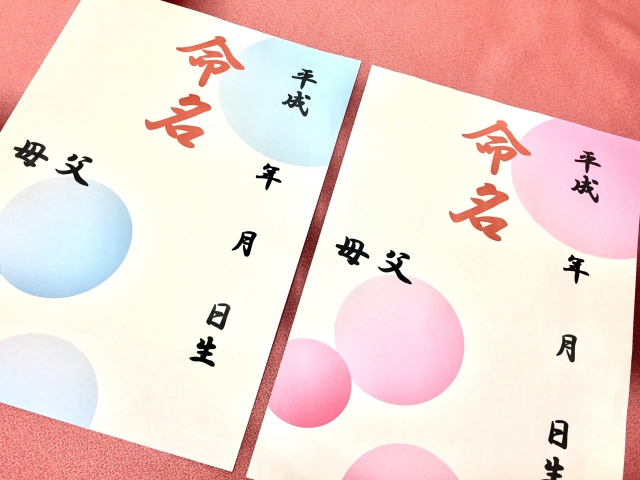
お七夜は、生まれて7日目に命名式やお祝い膳を囲むのが一般的ですが、赤ちゃんやママの体調を考えて行ってくださいね♪
お七夜をしようと考えているけど、いつすればいいのか分からない!と悩みますよね。
そもそも基本的なやり方や流れってどうやるの?と思うママパパも多いのではないでしょうか。
お七夜はいつすべきなのか、やり方や流れを解説しますので、参考にしてみてください♪
お七夜はするのはいつ?
お七夜は、赤ちゃんが生まれて7日目に行うのが一般的。
生まれた日を1日とカウントする昔の数え方と、生まれた日を0日とカウントする現在の医学的な数え方があります。
生後7日目を目安とした前後で、赤ちゃんやママの体調が良い時などにするのがおすすめ♪
基本的やり方や流れを紹介!
- 1はじめの挨拶
ママパパから、集まってくれた方々への挨拶でスタート!
長くて難しいスピーチは必要ありません。
当日集まってくれた感謝や、産前から出産までのサポートに対するお礼の気持ちを素直に伝えてみてくださいね♪
- 2名前・名前の由来をお披露目
挨拶が終わったら、さっそくお七夜のメインともいえる命名式!
お七夜の前日までに名前を決め、名前を披露するための「命名書」を用意しておくとスムーズですよ!
当日家族や親族の前で記入したい場合は、毛筆や筆ペン、半紙なども一緒に用意しておきましょう♪
通常の半紙のほか、「命名紙」なども販売しています。
イラストが入ったかわいらしいものもあるので、デザインにもこだわりたい方はチェックしてみてくださいね♪
- 3祝い膳を食べる
名前を披露した後は、集まった家族や親族と一緒に食事会。
お祝い膳を用意したり、産後間もない赤ちゃんを連れて外食したりするのは大変なので、デリバリーを活用して自宅で行うのがおすすめ!
和食を選ぶ場合は、尾頭付きの鯛や赤飯、紅白なますなど、縁起物を取り入れてみてもいいですね♪
他にも、華やかなオードブルなど洋食を選んでもOK!
- 4記念の手形・足形をとる
お七夜の記念に、赤ちゃんの手形や足形を取るのもおすすめ。
急に足や手に顔料を塗るとびっくりしてしまうので、赤ちゃんの機嫌がいい時や寝ている間に撮るといいですよ!
かわいい手形、足形は素敵な想い出になりますね♪
- 5記念撮影
最後は記念撮影で、命名書や手形・足形など、お七夜のなかで作ったアイテムと一緒に撮影するのもおすすめ♪
赤ちゃんが成長した後で見返したとき、たくさんの人に愛されて生まれてきたんだよ、と伝えるきっかけにもなりますよ!
あくまでも基本的な流れになりますので、ご家庭に合ったスタイルで進めてみてくださいね♪
お七夜の注意点やポイント
お七夜は、昔から行われてきた行事ですが、何をするかなどにこだわっていると、家族に負担をかけてしまう可能性が。
お七夜をする際にはどのような点に気をつければよいか、紹介します!
計画しているママパパは、注意点やポイントを念頭に置いて計画を立ててくださいね!
ママと赤ちゃんの体調が最優先
お七夜をするときは、ママと赤ちゃんの体調が最優先!
生後7日頃は赤ちゃんが生まれて間もない時期であり、ママも出産直後のため、体調がまだ落ち着いていません。
お七夜をする予定があっても、体調不良で難しい場合は、日を改めて行うようにしてくださいね!
開催場所の確認
慣習的には父親の実家でする行事とされてきたため、あらかじめどちらの家でお七夜をするか相談しておくのがおすすめ!
事前に相談しておくと、両家に余計な不和を発生させずに、楽しくお七夜を終えられますよ♪
もし父方のおじいちゃんおばあちゃんが伝統を重んじる地域に住んでいた場合は、早めに相談しておくといいですね。
里帰りなど長期不在の場合は、妊娠中に早めにいつするのか相談しておくのもおすすめです。
お七夜をするときに知っておきたいマナーを紹介!

お七夜の流れについてのマナーは特にありませんが、命名紙の書き方には順番がありますので、間違えないように注意して書きましょう!
伝統的な行事でもあるお七夜だから、マナーがあるなら知っておきたい!と思いますよね。
そこでお七夜のマナーや命名書の書き方など紹介します!
実際に準備する際、参考にしてみてください♪
お七夜のマナーとは?
お七夜の流れ自体にはマナーはありません。
ただし、お七夜に招待されたら、おもてなしを受けながらお祝いするのが習わしのため、参加者はお祝い金を持参するのが一般的です。
お祝い金の相場
お七夜のお祝い金は、お食事代程度をお包みすると考えておきましょう。
お祝い金の相場は、5,000円~1万円程度が一般的な目安。
お祝いには品物も喜ばれる
お七夜のお祝い金に加え、品物を贈ってもOK。
お祝い金と一緒にベビーグッズや育児用品、菓子折りなどの手土産を持参もおすすめです。
果物や生花、お祝いの席でデザートとして食べられるケーキなどももらうと嬉しいですよね♪
相手の方の家族構成を考えて、使えるもの、喜んでいただけるものを選んであげてくださいね!
お返しの内祝いはどうする?
基本的にはお祝い膳がお返しになります。
お招きしたお客さまに手ぶらで帰ってもらうのは気が引ける、という場合は、手土産を準備するのもおすすめ!
のしには赤ちゃんの名前を記し、お招きした方の負担にならない程度のものを、内祝いとして準備してくださいね♪
命名書の書き方やマナー
命名式で使用するため、間違えられない命名書。
でも、正しい書き方って分からないですよね。
そこで、書き方を詳しく解説しますので、参考にしてみてください♪
正式な命名紙の書き方
正式な命名紙は、「奉書紙(ほうしょし・ほうしょがみ)」を2枚使います。
- 表面が外側、裏面が内側になるように、下から上へ、上下半分に折り上げる。
- 輪(折り目)を下にして置き、左から3分の1の所で折る。
- 次に、右から3分の1の所で折り重ね、三つ折りにする。
- 右側 右面の中央に「命名」と書く。
- 中央 右側に小さく「親の名前、続柄」、中央に大きく「赤ちゃんの名前」、左側に小さく「生年月日」を書く。
- 左側 右側に小さく「命名の日付」、中央に「両親の名前」、名付け親がいる場合は左側に「命名者の名前」を書く。
- 表面が下になるように、うつぶせにして置く。
- 中央に命名書を置き、左から3分の1の所で折る。
- 次に、右から3分の1の所で折り重ね、三つ折りにする。
- 中央に置いた命名書のサイズに合わせて上下を裏側へ折る。
- 上包みの表に「命名」と書く。
略式の命名紙の書き方
略式の命名紙には決まりがなく、かわいいデザインの命名紙もたくさん販売されていますので、好みのものを選んでくださいね♪
- 右側 「赤ちゃんの生年月日」を書く。
- 中央 上部に「命名」と書き、その下に大きく「赤ちゃんの名前」を書く。
「ふりがな」は書いておくと、見た人に覚えてもらいやすくなりますよ♪ - 左側 「両親の名前」を書く。
名付け親の名前を書く場合は、一番左のスペースに「命名者 〇〇」と書く。
お七夜後の行事
お七夜の後も、赤ちゃんの行事はたくさんありますよ!
1歳までのお祝いを紹介しますので、参考にしてみてください♪
ニューボーンフォトでは、生後1カ月くらいまでの赤ちゃんを撮影します。
新生児らしい姿を残すため、おくるみなどでまるまった姿勢で写真を撮るのもかわいいですよ!
男の子は生後31日目~32日目、女の子は生後32日目~33日目を目安にお宮参りをします。
お宮参りは、赤ちゃんの誕生を神様に報告し、今後の健やかな成長を祈る行事。
おじいちゃんおばあちゃんを呼んで、一緒に写真撮影してもいいですね♪
お食い初めは、生後100日を記念して、赤ちゃんに料理を食べさせる真似をする行事。
一生食べ物に困らないようにと願う意味があります。
お食い初めコースなど準備しているお店もありますので、確認してみてください!
ハーフバースデーでは、半年の成長をお祝いします。
離乳食やプレゼントと一緒に写真を撮ったり、ドレスを着て撮るのも素敵ですね♪
1歳の誕生日に重さ一升の餅を持たせる行事。
子どもの健康や一生食べ物に困らないように祈る意味があります。
一升餅の他に、一升米やパンもあります。
子どもが背負いやすいようにリュックや巾着などもありますので、是非チェックしてみてくださいね!
お七夜はする?しない?のまとめ

- 生まれて最初のお祝いだが、ライフスタイルによって、する・しないの選択は自由
- するメリットは、赤ちゃんの名前を正式に発表でき、家族や祖父母と楽しい時間を過ごせる
- するデメリットは、準備に時間がかかる、ママの体調が不安定な時期に準備をする必要がある
- しないメリットは、家族の納得のいく方法で、お祝いを楽しみながら記念を残せる
- しないデメリットは、名前を正式に伝える場がない、祖父母と集まる機会がない
- お七夜は、生まれて7日目に命名式やお祝い膳を囲むのが一般的だが、赤ちゃんやママの体調を考えて行う
- お七夜自体にマナーはないが、お呼ばれしたときは、お祝い金を持参するのが一般的
- お七夜後にも、お宮参りやお食い初め、一升餅などイベントはたくさんある
お七夜は生まれて初めてのお祝い事、家族みんなで楽しい時間を過ごしたいですよね。
するしないを選ぶのは自由なので、赤ちゃんやママの体調と相談して決めてくださいね♪
お七夜後にもたくさんの行事があるので、ひとつひとつ赤ちゃんの成長を楽しみましょう!
お祝いを彩る「メモリアルフラッグ」付きなので、命名書と一緒に飾るのもおすすめ♪
名前は初めて親から子どもへのプレゼント、しっかり形に残せます。
命名書と家族みんなで写真撮影すると、素敵な記念になりますよ!
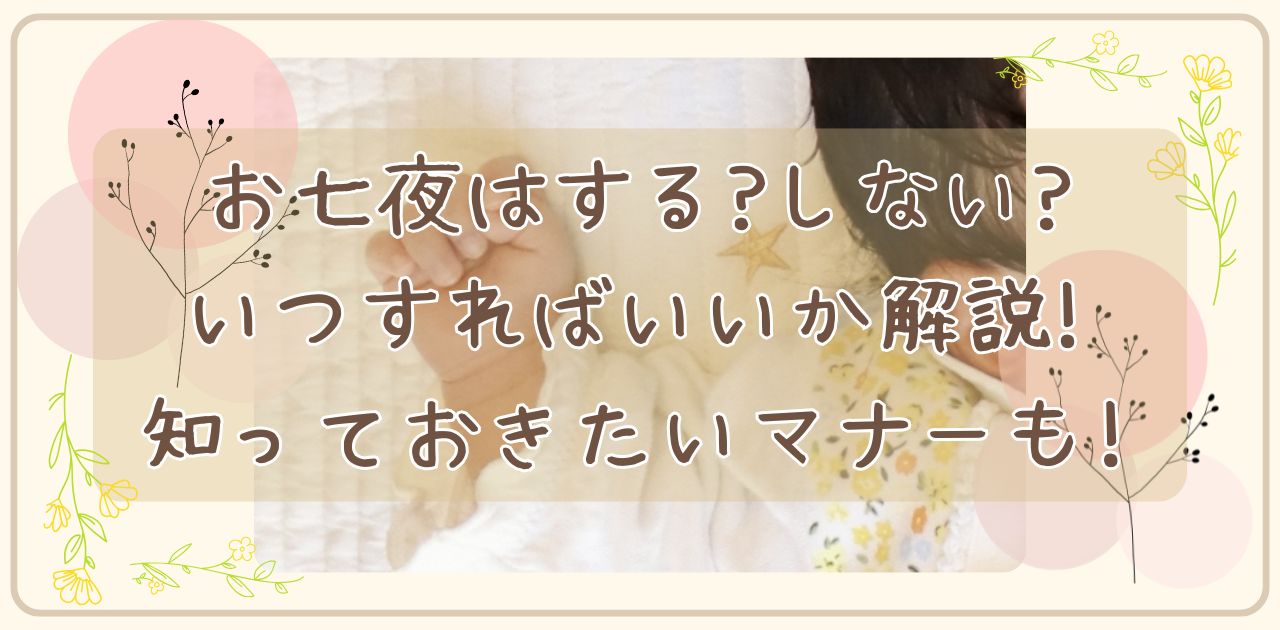


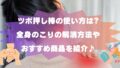
コメント